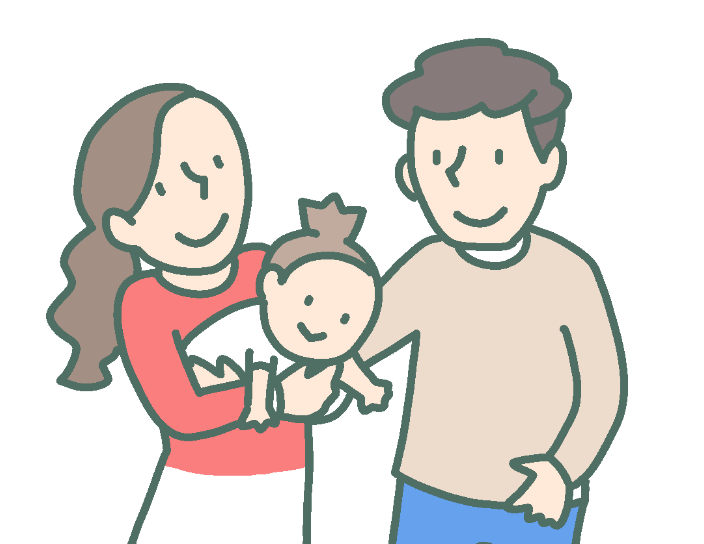
Childcare support 子育てサポート
ライフステージの
変化にも対応
穴吹工務店では、社員一人一人が最大限能力を発揮し、生き生きと働ける環境を提供することが重要だと考えています。ライフステージが変化して、仕事と子育ての両立が必要になった場合も安心して働き続けられるように、 さまざまなサポート体制の整備に力を入れています。

くるみんマークを取得
次世代育成支援対策推進法に基づき、子育て支援に積極的に取り組む企業として認定されている証が「くるみんマーク」です。2016年7月、穴吹工務店は香川県の建設業では初めて、この認定を取得しました。これからも業界の先駆けとして、働きやすい環境づくりに取り組んでまいります。
子育てを支援する制度
妊娠から出産まで
-
妊娠中の通勤緩和・休憩措置など
妊娠中や出産後1年未満の方は、時間外勤務・休日出勤・深夜業の免除や通勤緩和などの措置を受けられます。
-
産前産後休業
出産予定日を含む6週間前から休業ができ、出産後は8週間まで休業ができます。健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料は免除されます。
-
年次有給休暇の取得
産前休業・産後休業の前に、年休を合わせて取得することができます。
-
配偶者出産による特別休暇
配偶者が出産したときに1日の特別休暇を取得できます。(出産日から1カ月以内)
-
出生時育児休業(産後パパ育休)
男性社員が、子どもの出生後8週間以内に4週間までの育児休業を取得できます。初めに申出れば、2回に分割して取得できます。
※養子の場合等は女性も取得可能
※配偶者が専業主婦(夫)でも取得可能 -
女性の健康や出産、子育てのための相談窓口
からだの不調、気になる症状、妊娠、出産に関する悩みや不安などについて、チャットやTV電話で、匿名で医師や看護師に直接相談できます。また、公私問わず、育児に関する悩みも相談できる社外相談窓口「EAP」も利用できます。
育休から復職まで
-
育休制度
子どもが1歳になるまで男女の性別を問わず、夫婦同時にはもちろん、2回に分割して休業もできます。健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料は免除されます。
※配偶者が専業主婦(夫)でも取得可能
※最初の連続した5営業日のみ有給扱い -
パパママ育休プラス
父母両方が育休を取る場合は、あとから取得した側が子どもが1歳2カ月になるまで育休を延長可能です。
-
育児休業制度の延長
子どもが保育園に入れないなどのやむを得ない事情がある場合に、育児休業を延長することができます。
-
復職前面談
復職前に上司や人事担当者との面談を行っています。復職後に担当する業務の内容や勤務形態(時短取得等)について相談することで、スムーズに復職できるようにサポートしています。
育児と仕事の両立
-
時短勤務
子どもが小学校3年生になるまで、1週につき10時間以内で短時間勤務が可能です。(給与控除あり)
-
子の看護休暇
小学校3年生までの子どもが傷病による看護や、健康診断・予防接種受診、学級閉鎖(インフルエンザ等)などで付き添いが必要になった場合に子ども1人につき年5日間の有給休暇が取得できます。
※入園(入学)式、卒園式にも取得可能
-
育児サービス利用支援制度
小学校3年生までの子どもに育児サービス(ベビーシッター・延長保育等)を利用した場合に、その利用額の半額を補助する等があります。
※育児サービス:通常保育(平日8時~18時までの10時間相当)の枠を超えて保育を依頼するサービス
-
時短フレックス
時短勤務者のうち、条件を満たす方についてはフレックスタイム制が適用され、始業・就業の時刻や働く時間を選択で可能になります。仕事と育児の両立を図りながら、効率的に働くことができます。
-
職種転換
自身のキャリア志向やライフイベントなどに応じて、職種(働き方)を選択できます。会社は選択された職種に従い職務・役割・勤務地等の変更を検討します。
-
時間外労働の制限・深夜業の免除
小学6年生までの子どもを養育する場合に、時間外労働を月24時間、年150時間を超えることができないように制限し、深夜業を免除できます。
-
産前産後の症状に対する措置
妊娠中および出産後1年以内に医師等から指導を受けたとき、業務内容の軽減や勤務時間の短縮などを請求でき、休業が必要な場合は特別休暇を取得できます。
-
積立保存休暇
子どもの傷病による療養時や家族の看護により休暇が必要となり、年次有給休暇を全日数消化している場合に、積立保存休暇を取得することができます。
支給金制度
-
「出産育児一時金」の支給
社員または被扶養者の出産について、全国土木建築国民健康保険組合より一時金50万円が支給されます。
-
「出産手当金」の支給
出産のために仕事を休み、無給の時に、全国土木建築国民健康保険組合から出産手当金が支給されます。
-
「育児時短休業給付金」の支給
2歳未満の子どもを養育するために育児時短就業している場合に、条件を満たせば給与とは別に雇用保険から給付金が支給されます。
-
「出生後休業支援給付金」の支給
子どもの出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、雇用保険から育児休業給付金と併せて最大28日間支給されます。
-
養育期間の年金額計算の特例
3歳未満の子どもを育てるために時短勤務などで給料が減った場合に、その期間にかかる将来の年金は、給料が下がる前の金額をもとに計算されます。
-
「育児休業給付」の支給
育児休業を取得した場合に、雇用保険から給付金が支給されます。(育児休業の延長時には条件により給付が認められない場合もあります)
育休取得者の声

社内の制度を活用して
3度の産休・育休と3度の復職を経験。
Y.Sさん 2008年入社
東日本支社
静岡支店総務課 兼 業務部引渡管理課 係長(所属・役職は取材当時)
産休・育休取得時期と取得期間
- 2018年:産休・育休(第一子) 599日
- 2020年:産休・育休(第二子) 436日
- 2022年:産休・育休(第三子) 408日
2018年から2022年まで、3回も立て続けに産休・育休を取得しましたが、そのたびに職場で「おめでとう!なんとかなるから大丈夫!」と温かい声をかけていただき、とても心強かったです。現在は6歳、4歳、2歳の子育て中で、9:00~16:00の時短勤務で働いています。子どもの送迎があるので、時間内に業務を終えられるように計画的に取り組んでいます。半日だけ園の行事がある場合などは、在宅勤務と半休を組み合わせるなど工夫しています。そのほか、子どもの体調不良などで急にお休みが必要になることもありますが、「会社のことはなんとかなるから、子どもといてあげて」と言ってもらえる職場に、感謝してもしきれないほど支えてもらっています。
私が心かげているのは、一人で抱え込まずに『報・連・相』で共有することです。仕事の場合は早めにフォローをお願いし、家庭ではミールキットや冷凍食品を活用。ロボット掃除機や洗濯乾燥機もフル稼働しています。仕事も家庭も大変なことはありますが、仕事が忙しいときも(半ば強制的に)考えすぎずリフレッシュできています。両方あるからこそ、うまく回っていると思います。
上司や同僚からの声
-
3度の育休・復職すべてのタイミングで上司を務め、現在は兼務上司です。もともと時間の使い方が上手く、自分と周囲の状況をよく見て動ける方だと思います。たとえば、保育園からの急な呼び出しの際にも、「ここまで対応済みで、あとはこれとこれをお願いします」と明確なので、こちらも負担を感じることなく引き継げます。復職のたびにパワーアップしているようで、周りも彼女から元気をもらっています。子育てを楽しみ、人を育てる経験をキャリアアップに生かし、これからも周りの皆さんを支えてほしいと思います。

上司Nさん
-
産休・育休・復職を複数回経験されていることで、家庭と職場との気持ちの切り替えや、時短勤務・有給取得・在宅勤務などの制度の効果的な利用方法に関する知見がとても高く、同じような状況にある社員にとって模範となる存在だと思います。本人のコメントから仕事と家庭の両面があることをポジティブにとらえている姿勢も伝わり、非常に共感・好感を持ちました。仕事が忙しい中でも家庭と両立させられるY.Sさんの視点で、業務効率の改善や無駄の削減に関しても、鋭い提案や指摘を期待しています。

上司Tさん

男性の育休は当たり前。
生後1カ月の育児の大変さと喜びを知る。
Y.Kさん 2017年入社
業務管理部 人財開発室 採用課 主任(所属・役職は取材当時)
産休・育休取得時期と取得期間
- 2024年:育休 約1カ月
「子どもが生まれたら"必ず"育休を取る!」と決めていました。自分にとって、家族と過ごす最初の時間は何よりも大切だと感じていたからです。上司に妻の妊娠を報告した際に、開口一番「ぜひ育休取ってね。期間はどうしようか?」と前向きな言葉をかけていただいたことがとても印象に残っています。
実際に育休を取得したのは、3月上旬から4月上旬までの約1カ月間です。この時期は、私の所属する採用課が多くの仕事を抱える繁忙期。限られた時間の中での引き継ぎは大変でしたが、課内の全面的な協力により準備を進めることができました。この時、多くの社員や取引先の方々から応援や温かい言葉をいただき、本当に励みになりました。
育休中は、初めてのことばかりで戸惑いながらも、生後間もない我が子と過ごす日々の中で、育児の大変さと同時に大きな喜びを知りました。かけがえのない経験だったと感じています。
上司や同僚からの声
-
育休の相談を受けたとき、人生の大切な節目を上司として支えたいと強く思いました。ちょうど繁忙期と重なっており、しかも彼は新卒採用業務の実務面のほぼ全体を動かしていましたが、早い段階で相談をしてくれたおかげで、課内でうまく引き継ぐことができました。中でも課に加わって1年ほどだった後輩のOさんは、実際に業務を担当することで短期間で大きく成長できたと思います。育休は、取得した本人が人としての成長や幸福感を得るだけでなく、周囲のメンバーにとっても成長の機会となることを実感できました。

上司Wさん
-
私自身、育休から復帰して半年ほどで、しかも時短勤務中だったため、「彼の不在をカバーできるだろうか」と正直不安がありました。でも、事前にしっかりと業務分担や引き継ぎをしてくれたおかげで、なんとかやりきることができました。この経験を通じて、「より効率的に働くにはどうすればいいか」を改めて考える良いきっかけにもなりました。育休取得に不安を抱いている方には、ぜひ彼の事例を参考に「穴吹工務店では、男女を問わず育休を取るのは当たり前」と感じていただきたいと思います。

同僚Kさん